
Alice Mabel Bacon (1858-1918)
 五人の女子留学生のひとり山川捨松はベーコン家に引き取られて養育されたため、アリス・ベーコンと梅子も幼馴染といってよい関係でしたが、梅子に再度の留学を勧めたのも、時には助言を与え、励ましてくれる少し年長の友人であったアリスでした。アリス・ベーコンはコネチカット州ニューヘイヴンに生れました。1881年ハーヴァード大学・学士検定試験で学士号を取得し、1883年ヴァージニア州ハンプトン師範学校の教師になりましたが、山川捨松、津田梅子らの招聘により、1888(明治21)年に任期一年の約束で華族女学校英語教師として来日しました。在職中は日本人の生活、特に日本女性の生活に深い関心を寄せ、教授の傍ら各地を旅行して日本女性の風俗習慣を研究し、帰国後の1891年にその成果をまとめてJapanese Girls and Women として出版しています。
彼女の存在は梅子にアメリカを身近に感じさせる役割をも果たしました。梅子は、よりよい教育者になるためには自らがさらにアメリカで高等教育を受けなければならないと実感するようになり、最初の留学時代に知己となったメアリ・モリス Mary Morris という協力者に相談したところ、モリスがブリンマー大学学長・ローズに交渉し、授業料および寮費の免除という待遇で、しかも華族女学校には在職したままの形で2年間の留学が許可される運びとなったのです。アリス・ベーコンは1900年4月に再び来日し、津田梅子を助けて女子英学塾開校の準備を進めました。開校後は一番町の校舎で数名の塾生と起居を共にしつつ無給で授業を受け持つ傍ら、東京女子師範学校でも教え、2年後に帰国しました。1905年48歳で三度来日、翌年2月に帰米したのが最後の訪日となりました。1918年5月18日、ニューヘイヴンにて57歳で永眠しました。
五人の女子留学生のひとり山川捨松はベーコン家に引き取られて養育されたため、アリス・ベーコンと梅子も幼馴染といってよい関係でしたが、梅子に再度の留学を勧めたのも、時には助言を与え、励ましてくれる少し年長の友人であったアリスでした。アリス・ベーコンはコネチカット州ニューヘイヴンに生れました。1881年ハーヴァード大学・学士検定試験で学士号を取得し、1883年ヴァージニア州ハンプトン師範学校の教師になりましたが、山川捨松、津田梅子らの招聘により、1888(明治21)年に任期一年の約束で華族女学校英語教師として来日しました。在職中は日本人の生活、特に日本女性の生活に深い関心を寄せ、教授の傍ら各地を旅行して日本女性の風俗習慣を研究し、帰国後の1891年にその成果をまとめてJapanese Girls and Women として出版しています。
彼女の存在は梅子にアメリカを身近に感じさせる役割をも果たしました。梅子は、よりよい教育者になるためには自らがさらにアメリカで高等教育を受けなければならないと実感するようになり、最初の留学時代に知己となったメアリ・モリス Mary Morris という協力者に相談したところ、モリスがブリンマー大学学長・ローズに交渉し、授業料および寮費の免除という待遇で、しかも華族女学校には在職したままの形で2年間の留学が許可される運びとなったのです。アリス・ベーコンは1900年4月に再び来日し、津田梅子を助けて女子英学塾開校の準備を進めました。開校後は一番町の校舎で数名の塾生と起居を共にしつつ無給で授業を受け持つ傍ら、東京女子師範学校でも教え、2年後に帰国しました。1905年48歳で三度来日、翌年2月に帰米したのが最後の訪日となりました。1918年5月18日、ニューヘイヴンにて57歳で永眠しました。
Anna C. Hartshorne (1860-1957)
 ハーツホン家は古いクウェイカー教徒の家柄で、父ヘンリーはペンシルヴェニア大学出身の医者でしたが、一人娘のアナの成長に伴って女子教育にも関心を持ちました。アナ・ハーツホンは父が校長を務めていたハラウンド・スクール(クウェイカーの女子のための全寮制高等学校)を出て、フィラデルフィアの美術学校で絵画を習得しました。ブリンマー大学初代学長のジェームズ・E・ローズとヘンリーとはクウェイカーとして親しく、双方の娘同志も親しかったため、アナ・ハーツホンは正規の学生ではありませんでしたが、大学にはかなり自由に出入りしていました。梅子とアナがはじめて出会ったのも、ローズ学長の娘にドイツ語を教えていたミス・チェインバリンの部屋であったということです。アナ・ハーツホンはブリンマー時代の梅子について、つぎのように述べています。「わたしがはじめてミス・ツダにあったのは、彼女がブリンマーの新入生のときであった。彼女は二十五才になったばかりで、年よりはわかく見えたが、人格が出来ており、重みもあって、他の学生よりは年上に見えた。・・・その後わたしは、ミス・ツダの学校内における人望や、研究に、特に専攻学科の生物学の研究にすばらしい成績をあげていることを耳にした」
(吉川利一著『津田梅子伝』, p176)
ハーツホン家は古いクウェイカー教徒の家柄で、父ヘンリーはペンシルヴェニア大学出身の医者でしたが、一人娘のアナの成長に伴って女子教育にも関心を持ちました。アナ・ハーツホンは父が校長を務めていたハラウンド・スクール(クウェイカーの女子のための全寮制高等学校)を出て、フィラデルフィアの美術学校で絵画を習得しました。ブリンマー大学初代学長のジェームズ・E・ローズとヘンリーとはクウェイカーとして親しく、双方の娘同志も親しかったため、アナ・ハーツホンは正規の学生ではありませんでしたが、大学にはかなり自由に出入りしていました。梅子とアナがはじめて出会ったのも、ローズ学長の娘にドイツ語を教えていたミス・チェインバリンの部屋であったということです。アナ・ハーツホンはブリンマー時代の梅子について、つぎのように述べています。「わたしがはじめてミス・ツダにあったのは、彼女がブリンマーの新入生のときであった。彼女は二十五才になったばかりで、年よりはわかく見えたが、人格が出来ており、重みもあって、他の学生よりは年上に見えた。・・・その後わたしは、ミス・ツダの学校内における人望や、研究に、特に専攻学科の生物学の研究にすばらしい成績をあげていることを耳にした」
(吉川利一著『津田梅子伝』, p176)
ブリンマー大学 Bryn Mawr College
ブリンマー大学は、クウェイカー教徒の医師であり実業家でもあったジョゼフ・W・テイラー Dr.Joseph W.Taylorの遺産をもとに創立され、1885年9月に開校式を挙げました。フィラデルフィアの北西10マイルほどにあるブリンマーという町にあり、津田梅子が留学した1889年に最初の卒業生を出している。ヴァッサー Vassar College、ウェルズレー Wellesley College、スミス Smith Collegeなどに比べて規模は小さかったのですが、クウェイカー派 Quakerに属し、極めて厳格な教育で知られました。当時の学生数は150人余だったが、教授陣には著名な学者が多く、修業年限は4年、学科には文学科、生物学科、ギリシア語科、ラテン語科などがありました。
1880年、テイラーはハヴァフォード大学 Havaford College の女性版をイメージし、クウェイカー教徒によって後援される上流階級の女性のための大学を設立するための基金を寄付しました。優れた能力を持つ教員養成を念頭に置いていたテイラーだったが、特に重視したのは、子どもの人格形成に多大な影響を及ぼす母に、また、心豊かな家庭を維持すべき妻となる女性たちに、良質の高等教育を与えたいということでした。テイラーの教育観は、19世紀前半の女子神学校(セミナリー)の教育理念を継承するもので、家庭性を重視した、キリスト教徒の女性育成を目指すものでした。
テイラーのこの意向を根底から覆したのがM・ケアリ・トマス M.Carey Thomas でした。トマスの父やその他の親族がテイラーの理事会のメンバーであった関係で、1884年に学部長のポジションを与えられた彼女は、大学の創立と形成に深く関与することになります。トマスは自らが受けたコーネル大学 Cornell University やヨーロッパの高等教育のあり方、東部のいくつかの大学の視察に基づいて、「道徳修養から学術的厳格さを重視」する方向へと転換を図ることに成功しました。トマスは、開学前の1884年から1894年までを学部長として、1894年から1922年までを学長として、ブリンマー大学初期の大学形成および教育理念の具現化に最大の影響力を及ぼしたカリスマ的教育者となりました。なお、第一代学長にはジェームズ・E・ローズ James E.Rhoads が就任し、トマスの良き協力者となりました。
トマスは、何よりもブリンマー大学をエリート大学の直系の教育機関として位置付ようとし、カリキュラムにおいても全米で最高の水準のものを女性に与えるよう努めました。女性の高等教育機関としては最初の大学院を設立したのもブリンマー大学です。
津田梅子がブリンマー大学留学時代に着用したキャップ・アンド・ガウン
 津田梅子留学当時(1889年9月~1892年6月)の学部長であり第2代学長となったM・ケアリ・トマス M.Carey Thomasは、ジョンズ・ホプキンス大学Johns Hopkins University やライプチヒ大学 Universitat Leipzigをブリンマー大学のモデルとしましたが、大学の表出するイメージにも極めて敏感で、学内の建築様式はオックスフォード大学 Oxford Universityをモデルとして学問の威厳を示すことに配慮したほか、学生・教授たちが正装時に着用する帽子とガウンなどがもたらす象徴的意味にも特別な配慮を示しました。
津田梅子留学当時(1889年9月~1892年6月)の学部長であり第2代学長となったM・ケアリ・トマス M.Carey Thomasは、ジョンズ・ホプキンス大学Johns Hopkins University やライプチヒ大学 Universitat Leipzigをブリンマー大学のモデルとしましたが、大学の表出するイメージにも極めて敏感で、学内の建築様式はオックスフォード大学 Oxford Universityをモデルとして学問の威厳を示すことに配慮したほか、学生・教授たちが正装時に着用する帽子とガウンなどがもたらす象徴的意味にも特別な配慮を示しました。
生物学専攻と19世紀の学界潮流
津田梅子の留学期間は当初2年に限られていたため、選科生として1889年9月に入学し、専攻科目に生物学科を選びました。ブリンマー大学で1年半学んだ後、1891年2月から半年間、ニューヨーク州立オズウィゴー Oswego師範学校で教育および教授法を聴講しました。この師範学校はペスタロッチ Pestarozzi (1746-1827;スイスの教育家) の開発主義に基づく教授法で有名でした。
その後、1年間の留学延長が許可されたため、同年9月、再びブリンマーに戻り、前後2年半で生物学科の課程を修了しました。 2年目にはモーガン教授 Prof. Thomas Hunt Morgan (1866-1945)と共同で蛙の卵の発生を研究し、“Orientation of the Frogs Egg”と題する論文を著しています。この論文は〝The Quarterly Journal of Microscopical Science”Vol.35, 1894に掲載されました。
モーガンはその後コロンビア大学 Columbia University に移り、ショウジョウバエを使った染色体の研究を進め、1933年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。 梅子は1892(明治25)年8月、3年間の留学を終えて帰朝すると、引き続き華族女学校に勤務し、8年後の1900(明治33)年に女子英学塾を創立しました。
18世紀後半から19世紀にかけては学問の分化が進みましたが、生物学の分野では1809年にラマルク Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829;フランスの博物学者) が『動物哲学』を著し、1859年にはダーウィン Charles Darwin (1809-1882;イギリスの博物学者) が『種の起源』を出版して注目を集めた。スペンサー Herbert Spencer (1820-1903;イギリスの哲学者) やヘッケル Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919;ドイツの生物学者) は、ラマルクを継承して Neo-Lamarckismを提唱し、米国では特に、知名の学者がこの説を支持しました。ブリンマーのウィルソン教授 E.B.Wilson (1856-1939)もこの学派の有力な一人でした。



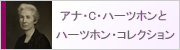
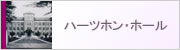
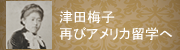

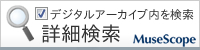
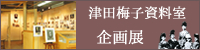
次の文は“The Education of Japanese Women”に含まれる、梅子の後日の回想です。
“When I returned home after my first visit to America, I was especially struck with the great difference between men and women, and the absolute power which the men held. The women were entirely dependent, having no means of self-support, since no employment or occupation was open to them, except that of teaching, and few were trained for teaching or were capable of it. A woman could hold no property in her own name, and her identity was merged in that of father, husband, or some male relative. Hence there was an utter lack of independent spirit.”
「最初の米国留学から帰ったとき、わたしが特に心をうたれたのは、男女間に非常な差別のあること、男子が絶対権をもっていることであった。婦人は全く隷属的で自活の道もなく、教えることのほかには仕事もなく、教師の訓練を受けるものも、教えることの出来るものも、殆どなかった。婦人は自分名義の財産をもつことが出来なかった。婦人は父とか、夫とか、男の親戚と一つに見られた。だから、婦人には独立の精神が全く欠けていた。」
(吉川利一著『津田梅子伝』津田同窓会,昭和31年,p.149)
その後、梅子は1885(明治18)年9月に伊藤博文の推薦で華族女学校奉職の辞令を受け、英語を担当することになりました。梅子の教育方針は実用の英語を教えることに重点を置くもので、会話、書取り、作文などに力を注ぎ、生徒の眼からみれば誠に厳しい教師だったということです。 華族女学校はもともと学習院女子部として1877(明治10)年から設けられていましたが、女子部が盛んになるに伴い四谷仲町の皇室付属地に校舎を建て、宮内省の直轄学校として独立しました。初代校長は谷干城、下田歌子はその学監となり、1885年10月授業開始、開校式は11月でした。小学、中学、各六年の過程を持ち、生徒数は150人、教職員は約30人でした。アメリカ合衆国東部でブリンマー大学 Bryn Mawr College が開校式を挙げたのも、同じく1885年9月23日のことでした。